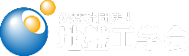【随時更新】防災学術連携体(62学協会)・地盤工学会も参加しています。
防災学術連携体(62学協会)は、防災減災・災害復興に関する学会ネットワークとして、平成28年1月9日に発足し、日本学術会議と連携して活動しております。
【防災学術連携体(62学協会)ホームページ】
![]()
http://janet-dr.com/
防災学術連携体ニュースレター
https://janet-dr.com/000_home/001_maga.html
日本学術会議 学術フォーラム/第16回防災学術連携シンポジウム
「関東大震災100年と防災減災科学」(7月8日)10時から18時
場所:日本学術会議 講堂+ZOOMウェビナーの併用
主催:日本学術会議(企画:防災減災学術連携委員会)、一般社団法人防災学術連携体
参加申込:https://ws.formzu.net/fgen/S93301949/
プログラム:https://janet-dr.com/060_event/20230708.html
ポスター:https://janet-dr.com/060_event/20230708/20230708_100th_leef.pdf
特設ページ開設のお知らせ(令和4年8月3日から続く大雨と災害について)
令和4年8月3日から続く大雨と災害について、特設ページが開設されました
https://janet-dr.com/050_saigaiji/2022/050_220818_gouu.html
学協会からの関係する情報がございましたら下記まで、ぜひお寄せください。
Webサイト担当 麓 絵理子 様宛
website@janet-dr.com
2022/5/9「自然災害を取り巻く環境はどう変化してきたか」
第13回防災学術連携シンポジウム・日本学術会議公開シンポジウム
主 催: 日本学術会議防災減災学術連携委員会、一般社団法人 防災学術連携体(62学協会)
日 時: 2022年5月9日(月)12:30~18:00
会 場: 日本学術会議講堂 および Zoom ウェビナーによるオンライン開催
申 込: https://ws.formzu.net/fgen/S79677929/
2021/11/6「防災教育と災害伝承への多様な視点-東日本大震災から 10 年を経て-」
防災学術連携体・特別シンポジウム
主 催: 一般社団法人 防災学術連携体(59学会)
日 時: 2021年11月6日(火)18:05~20:00
会 場: Zoom ウェビナーによるオンライン開催
申 込: https://ws.formzu.net/fgen/S52435646/
2021/11/6「防災教育と災害伝承」
防災推進国民大会 2021 セッション・第 12 回防災学術連携シンポジウム・日本学術会議公開シンポジウム
主 催: 日本学術会議、防災減災学術連携委員会、一般社団法人 防災学術連携体(59学会)
日 時: 2021年11月6日(火)14:30~16:00
会 場: Zoom ウェビナーによるオンライン開催
申 込: https://ws.formzu.net/fgen/S43949681/
2021/1/14「東日本大震災からの十年とこれから」 ~58学会、防災学術連携体の活動~
第11回防災学術連携シンポジウム・日本学術会議主催学術フォーラム
主 催: 日本学術会議 防災減災学術連携委員会、土木工学・建築学委員会、防災学術連携体(58学会)
日 時: 2021年1月14日(木曜日)午前10時~午後5時
場 所: 東京医科歯科大学 鈴木章夫記念講堂、およびネット同時配信
趣 旨: 2011年東日本大震災の甚大な被害から十年が過ぎます。東日本大震災以降も日本の各地で多くの自然災害が発生しました。これらの災害について、多くの学会は調査研究、記録、提言、支援などを続けてきました。大震災後十年を迎えるにあたり、防災学術連携体の各構成学会と日本学術会議の委員が、これまでの活動を振り返るとともに、今後の取り組みについて発表します。
なお、同時に、東日本大震災十周年「防災学術連携体58学会の記録」の冊子を作成し、参加者及び関係各所に配布します。
2020/10/3「複合災害への備えー withコロナ時代を生きる」
第5回防災推進国民大会における第10回防災学術連携シンポジウム・日本学術会議公開シンポジウム
主催:日本学術会議 防災減災学術連携委員会、土木工学・建築学委員会、防災学術連携体(58学会)
日時:2020 年 10 月 3日(土曜日)午後1時半~午後3時
会場:ネット同時配信
趣旨:新型コロナウィルスの感染拡大は日本全国、全世界に及んでいます。感染症への対策は続けねばならず、この間に生じる自然災害によって起こる複合災害にも警戒が必要です。日本は災害の多い国であり、南海トラフ地震、首都直下地震のみならず、気候変動の激化による豪雨災害
にも備えねばなりません。「with コロナの時代」に生きる私たちは、今後どのように複合災害に備えていくべきでしょうか。医療、気象、河川、地震、土木、建築、都市計画などの分野の専門家が集まり、知恵を結集して議論するとともに、一般市民への展開を図ります。
2019/10/19 第8回防災学術連携シンポジウム・日本学術会議公開シンポジウムを開催
防災学術連携体は、日本学術会議とともに内閣府の主催する防災推進国民大会に初回から参加し、セッションを設けています。初回は東京、第2回は仙台、第3回は東京で開催され、本年は第4回にあたり、伊勢湾台風(1959)から60年の年でもあり、南海トラフ地震の発生も心配されている名古屋市にて10月19日・20日に開催されます。次のセッションを設け、準備を進めておりますので、多くの方々のご参集を期待しております。
防災学術連携体代表幹事
米田雅子 (慶應義塾大学特任教授、日本学術会議会員、防災減災学術連携委員会委員長)
古谷誠章 (早稲田大学教授、日本建築学会前会長)
主 催:日本学術会議 防災減災学術連携委員会・防災学術連携体(57学会)
日 時:2019年10月19日(土)16時30分より18時まで
会 場:名古屋市ささしまライブ24エリア・メインホールB
テーマ:「あなたが知りたい防災科学の最前線―激化する気象災害に備えるー」
趣 旨:地域の防災力の強化に科学を役立てるため、市民の皆様が知りたい気象災害に関する防災科学の最前線を、各分野の専門家からわかりやすく伝えます。各分野の専門家と市民との相互交流を図り、地域や個人が準備すべき防災の備えに関する情報を参加者に提供し、防災力の強化を目指します。
参加費:無料(多くの市民の皆様や防災に関わる方々のご参加をお待ちしています。)
申込み:以下のURLより参加申し込みをお願いいたします。(当日の直接参加も可)
申し込みのURL:https://ws.formzu.net/fgen/S43949681/
詳細内容(ポスター)はこちら→ https://janet-dr.com/
参考:第4回防災推進国民大会HP:http://bosai-kokutai.jp/
2019/6/13 第2回「防災に関する日本学術会議・学協会・府省庁の連絡会」
-災害時医療と理工学分野の連携-
日 時:2019年6月13日(木)13:00~17:30
会 場:日本学術会議講堂(東京・乃木坂)
※ 本連絡会は日本学術会議の防災減災学術連携委員会として開催する
(本連絡会開催の10分前(12時50分)に上記委員会を開始予定)
※ 本連絡会は日本学術会議(会員・連携会員)、防災学術連携体(幹事、防災連携委員)の集まりですが、57会員学会の会員の皆様のご参加も自由です。
申し込みは不要ですので、当日に会場にいらしてください。
災害発生後の緊急時における医療活動は、人命を守る観点で極めて重要である。この活動を支えるためには、被災状況の把握、被災地までのあるいは被災地における交通・輸送の確保、病院・避難施設の安全・環境面の問題など、理工学の諸分野の技術や情報が展開される必要がある。
本連絡会では、災害発生直後の医療・看護活動をスムースに進めるための連携に的を絞り、各分野の情報交換を行うとともに、今後の連携のあり方と方策を考える。
2019/3/12 【当日ライブ配信】日本学術会議主催学術フォーラム 第7回防災学術連携シンポジウム
平成30年夏に複合的に連続発生した自然災害と学会調査報告
日時:2019 年 3月12日(火) 10:00~17:30
会 場:日本学術会議講堂
主 催:日本学術会議 防災減災学術連携委員会、防災学術連携体(56学会)
参加費:無料
申込み:事前申込はこちら。→https://ws.formzu.net/fgen/S44714662/ ( お申込みは終了いたしました)
【当日ライブ配信が行われます】⇒こちらよりご覧ください
平成30年の夏から秋にかけて、日本列島を自然災害が次々と襲った。平成30年6月18日大阪府北部地震が起こり、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)は広い範囲に同時多発的な大雨と土砂災害をもたらした。その後の記録的猛暑と連続して発生した台風、9月4日に上陸した台風21号は、百の観測点で強風記録を塗り替え、高潮と強風で関西国際空港を孤立させた。9月6日の北海道胆振東部地震は震度7を記録し、山地崩落や火力発電所の被災による北海道全域のブラックアウトを引き起こした。
防災学術連携体、56学会と日本学術会議は、これらの災害に対応して、ホームページに特設ページを設け、緊急集会、市民への緊急メッセージ、緊急報告会を開催し、各学会の情報を発信すると共に学会間の情報共有を図ってきた。
本シンポジウムでは、主に平成30年の夏に複合的に連続発生したこれらの自然災害に焦点を当て、各学会の調査報告を行う。さらに、今後、連鎖する気象災害にどう備えていけば良いのか、地震と気象災害などの複合災害にどう備えれば良いのかを議論する。
2018/11/8 学術会議シンポジウム「学術の法人制度に向けた提言」のご案内
学術を発展させる法人制度に向けた提言~公益法人法10周年~
日 時:2018 年11 月8 日(木)午後1 時30 分~ 5 時
場 所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7 丁目22 番地34 号)
日本学術会議公開シンポジウム
主 催:日本学術会議 科学者委員会 学協会連携分科会
日本学術協力財団 学協会運営支援委員会
参加費:無 料
申込み方法:下記申込みフォームよりお申込みください
https://ws.formzu.net/fgen/S82071163/
<< 趣 旨 >>
2018 年12 月に公益法人法の施行から十年を迎えるにあたり、日本
学術会議学協会連携分科会と日本学術協力財団学協会運営支援委員
会は、学術をより発展させるために、財務3 基準・連携組織体制度・
小規模学協会などに関する法人制度見直しへの提言案をまとめた。
本シンポジウムでは、提言案を報告するとともに、提言案に関して
会場の参加者と総合討論を行い、より良き提言にまとめる。
2018/10/13 日本学術会議公開シンポジウム / 第6回防災学術連携シンポジウム
「あなたが知りたい防災科学の最前線 首都直下地震に備える」
日時:2018 年 10 月 13 日(土)16:30 ~ 19:00
会 場 : 東京ビッグサイト会議棟7F国際会議場 交通アクセス
同フロアにてポスター掲示(13日・14日)
主 催 : 日本学術会議 防災減災学術連携委員会、防災学術連携体
参加費 : 無料(ご家族、お友達などと多くの方々のご参加により、有意義な会合にしたいと思います)
申込み : 事前申込はこちら。(当日の直接参加も可能と思います)
ご案内 : https://janet-dr.com/060_event/20181013/181013_000_leef.pdf
近年首都直下地震の発生が危惧されています。日本学術会議や防災学術連携体(56学会)には、様々な視点から、首都直下地震の災害の軽減に向けて研究を続けている研究者がいます。防災においては「自助・共助」「地域での連携」が大切で、消防団、町内会や自治会、学校や職場で、防災訓練や教育が続けられています。
シンポジウムでは、地域の防災力の強化に科学を役立てるため、市民の皆様が知りたい防災科学の最前線をわかりやすくお伝えします。
地盤工学会からは,セッション1 防災科学の最前線(その1:ハード関係)において
「首都直下地震による液状化被害について」と題して,国士舘大学の橋本隆雄会員が登壇いたします。
2018/9/10 防災学術連携体 西日本豪雨の緊急報告会開催
広い範囲にわたり記録的な大雨となった西日本豪雨(平成30 年7月豪雨)は、各地に河川の氾濫、土砂災害などの被害をもたらし200 名を超える犠牲者を出しています。政府は西日本豪雨災害を、豪雨災害では初めて「特定非常災害」に指定し、激甚災害に指定しました。
この豪雨災害による地域への影響は広域かつ長期に及び,さらに夏後半から秋にかけて台風や秋雨前線に伴う土砂災害の拡大などが懸念されることから、予断を許さない状況にあります。防災学術連携体(56 学会)は7 月9 日にホームページにこの豪雨災害のページを開設し、学会の調査情報、国土交通省・気象庁などの最新情報を掲載し、関係者間の情報共有に努めてきました。
7月16日には緊急集会を開催し、7月22 日には「西日本豪雨・市民への緊急メッセージ」を記者発表しました。日本学術会議と防災学術連携体は、被害の拡大を防ぐために、西日本豪雨に関する学会間の情報交流を進め、今後の対策を検討するために緊急報告会を開催します。
日 時:2018 年9 月10 日(月)13:00~17:30
場 所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7 丁目22 番地34 号)
日本学術会議公開シンポジウム・防災学術連携体緊急報告会
主 催:日本学術会議 防災減災学術連携委員会、土木工学・建築学委員会、防災学術連携体
参加費:無 料
申込はこちら(防災学術連携帯JANETの申し込みページへ遷移します)>>>申込みフォーム
「熊本地震・一周年報告会」(平成29年4月15日:日本学術会議公開シンポジウム/第3回 防災学術連携シンポジウム)
熊本県の公式行事「熊本地震 追悼・復興祈念行事」として共同開催することになりました。
15学会の発表、15学会のポスター発表、熊本県・熊本市からの発表と全体質疑を行います。
学術関係者と熊本県の皆様との交流を大切にし、相互理解と情報共有を進め、今後の熊本の復興に役立てたいと存じます。
関係者や関心のある方にご周知の上、ご参加いただけますと幸いです。
_________________________
【日本学術会議・防災学術連携体の関係者・参加学会会員の方々へ】
報告会の終了後に「熊本県の皆様と学術関係者による意見交換会」、報告会の翌日には「熊本復興視察ツアー」を予定しています。どうぞご参加下さい。
(★熊本県の関係者をのぞき、一般の方の参加は受け付けておりません)
日 時:平成29年4月15日(土曜日)11:00~18:20
会 場:熊本県庁本館 地下大会議室(熊本市中央区水前寺6-18-1)
主 催:日本学術会議、熊本県、防災学術連携体
参加費:無料、資料は事前にホームページに掲載予定
《Webサイト》:http://janet-dr.com/07_event/event14.html
《ご案内PDF》:http://janet-dr.com/07_event/170415sympo/170415sympo_leef.pdf
《申込みはこちら》:https://ws.formzu.net/fgen/S95969388/
「第2回防災学術連携シンポジウム:激甚化する台風・豪雨災害とその対策」(平成28年12月1日:日本学術会議主催公開シンポジウム)
平成28年12月1日(木曜日)に、日本学術会議主催公開シンポジウム「第2回防災学術連携シンポジウム:激甚化する台風・豪雨災害とその対策」が開催されます。
当学会の 小高猛司 理事が登壇いたします。是非ご参加くださいますようお願い申し上げます。
日 時:平成28年12月1日(木曜日)10:00~18:00
会 場:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
主 催:日本学術会議 防災減災・災害復興に関する学術連携委員会、防災学術連携体
申込方法:防災学術連携体ホームページ(以下ご参照)からお申込下さい。
《詳細Webサイト(申込み等)》:防災学術連携体ホームページ http://janet-dr.com/07_event/event13.html
《ご案内PDF》: 第2回防災学術連携シンポジウムリーフレット(1.18MB)
*プログラム等をご確認いただけます*
防災学術連携体「第一回防災推進国民大会」のご案内(平成28年8月27-28日)
本年8月27日と28日に内閣府主催により「第一回防災推進国民大会」が東京大学本郷キャンパスにおいて開催されます。
この大会では日本学術会議と防災学術連携体の共同主催により、以下の3つの催しが開かれます。
これらの催しは、事前申し込みは必要なく、参加費はすべて無料です。
会員の皆様、ご関係の皆様、ご家族の皆様のご参加、ご参集をお待ち致します。
《第一回防災推進国民大会サイト》 http://bosai-kokutai.jp/
① 8/28 「第1回防災学術連携シンポジウム」安田講堂
10:00-12:00 「52学会の結集による防災への挑戦?熊本地震における取組み」
http://janet-dr.com/01_home_info/20160828Sympo-1.pdf
② 8/28「2つのワークショップ」山上会館2階会議室
12:30-14:20 1「火山災害にどう備えるか」
14:40-16:30 2「東京圏の大地震にどう備えるか」
http://janet-dr.com/01_home_info/20160828WS-1.pdf
③ 08/27-28「防災学術連携体の紹介ポスター展示」安田講堂3階回廊
防災学術連携体「熊本県熊本地方の地震に関する緊急共同記者会見」の開催
この度、2016年4月14日21時26分頃、熊本地方でマグニチュード6.5の地震が発生しました。
防災学術連携体に所属する学会から専門家有志が集まり、この地震に関する緊急共同記者会見を行います。
※プレスリリース内容はこちら(481KB)
■防災学術連携体(50学会)では、ホームページに熊本県の地震のページを開設しました。
http://janet-dr.com